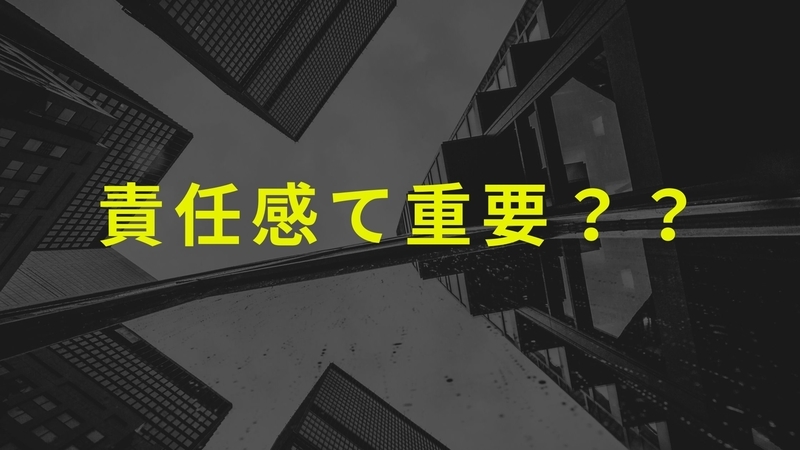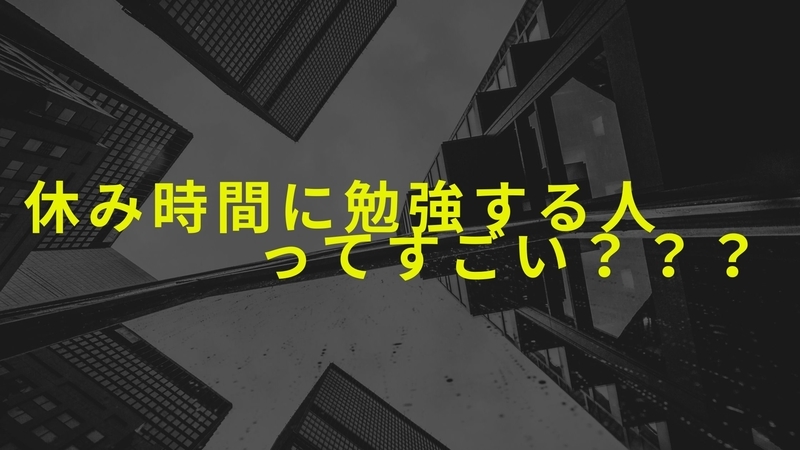・どのように子どもを理解していけば良いか知りたい
先日、『教師が子どもを理解することが必要な理由とその方法【教師に絶対的に必要なあり方です!!】』という記事を書きました。
 教師が子どもを理解することが必要な理由とその方法【教師に絶対的に必要なあり方です!!】
教師が子どもを理解することが必要な理由とその方法【教師に絶対的に必要なあり方です!!】
今回の記事では、これらを踏まえ、僕が子どもをどのように見ているのかについて、具体的な事例も含めて書いていきます。
今日の事例は、“責任感のある子ども”です。
同じ行動でも、その子の背景によって見方は変わってきますが、一例として参考にしていただければと思います。
・責任感のある子どもをどのように捉えるか
この記事を書く僕は、以下のような人間です
「小学校教員をしている」
「子ども理解に関心がある」
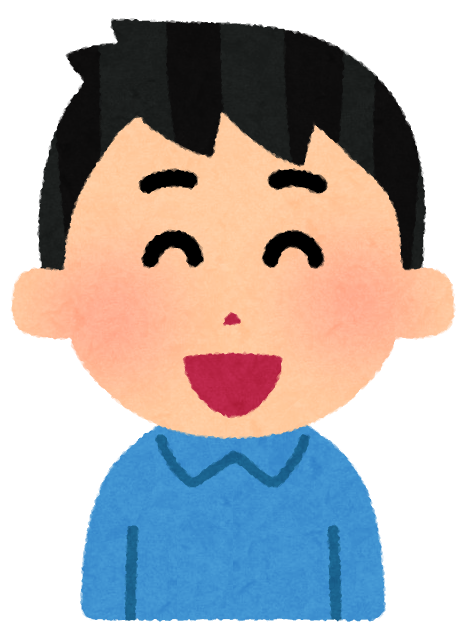
責任感のある子どもの事例
こんな子どもがいたとします。
同じ班の困っている子がいたら進んで助けようとする。
例えば同じ班の片付けができない子のサポートをする。
掃除をしなかったら、しっかりやるように注意をする。
席に座っていない時にはm席に座るように注意をする
体育の時に声を出していない子に対して声を出すように促す。
この子ってどんな子なんでしょう?自分らしく生きているのでしょうか?
その子を理解するうえで大切な問い
この子は一体誰のために責任感を強く感じているのか?
自分のため?友達のため?先生のため?
先生のために責任感を発揮してくれているのであれば、その子は先生に認められたいという思いで、先生にとって良いことをやっています。
“先生が認めてくれるから”というのは,自分の中の正義感で行なっていることではありません。
これでは、子どもは人の目を気にして行動する子に育っていきます。
もちろん、子どもが教師の都合良く動いてくれればそれはラクです。
でも、そのラクというのは全く良いはずありません。
あえて、難しく大変な方に進むべきです。
この子をどう捉えるか??
上の事例のような責任感のある子は果たしてリーダーでしょうか?
僕は、リーダーではないと思っています。
なぜなら、◯◯できない子を無理にやらせようとしかしていないからです。
これは、もはや“責任感がある”と言うよりもむしろ、
“みんながやっているからあなたもやって”
“一人だけしっかりしないのはズルイ”
というような同調圧力が働いていると感じてしまいます。
本当に責任感のある子であったら、◯◯できない子に対して注意をするというような対応はとらないと思います。その子に寄り添い、その子の気持ちを理解するところからスタートするはずです。
また、友達のできていないところに目がいってしまい注意する子は、なぜ注意するのか?を考えていきます。
上にも書きましたが、“先生に認められたい”というのもあるかもしれません。他にも、“◯◯だけズルイ”と感じてしまう何かがあるのか?発達段階的なものか?家庭的背景か?これまでの生活経験でそのようなことかあったのか?”などその子の内側にあるものを理解していこうとします。
そして僕の教師としての願いとしては、そのような子に対して、
“責任感のあることは良いことだから,みんながやっているのであれば◯◯できない子もするべき”という同質的な価値観から,“まあ,少しくらいできなくても良いよね。本人的には頑張っているよね”
という相手を理解しようとする違っているけど良いよねという異質同等の価値観に変わってほしいと願います。
また、こういう責任感のある子は,“担任の先生が◯◯できない子をこうしているから,自分もこうする”というように,担任の関わり方をよく見ているので、◯◯できない子を教師がどのように捉えるかということはもっとも大切なことだというのは言うまでもありません。
おわりに
子どもの見方について書いてきました。
今後もいろんな事例をもとに考えていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
では!!