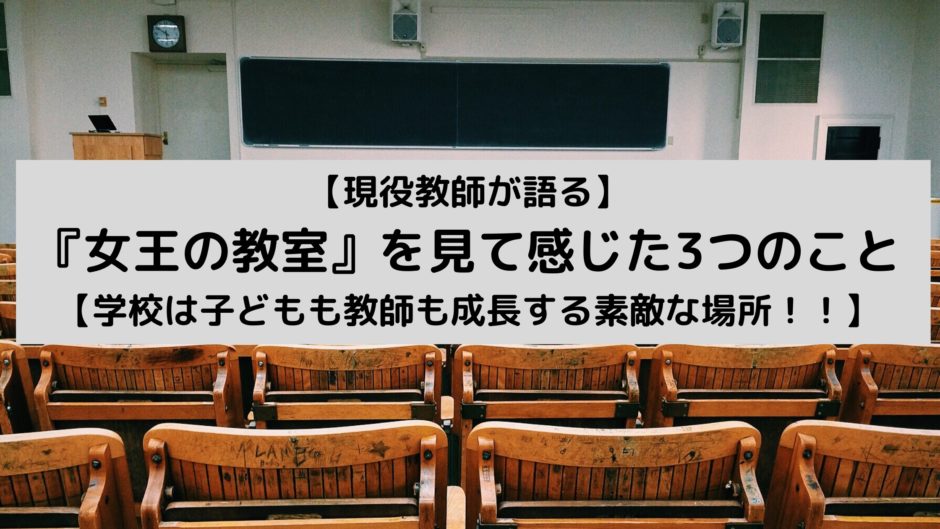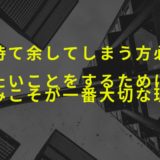・教育に興味がある
・女王の教室について興味がある
先日、久しぶりに女王の教室を見ました。僕が小学生のころやっていてめちゃくちゃハマっていていたドラマの一つです。このドラマのあらすじは、怖い先生である阿久津真矢(以下:真矢)を子どもたちが力を合わせてやっつけるのですが、実は先生は子どもたち思いの良い先生だったという内容です。
当時の僕は、このようにしか捉えていませんでしたが、この歳になって改めて見てみるとこのドラマは日本の社会システムや、教育の本質についてとても鋭く訴えいることが分かりました。
・女王の教室を見て感じた3つのこと
・女王の教室を見て教師として生かせること
・女王の教室を批判的に見る
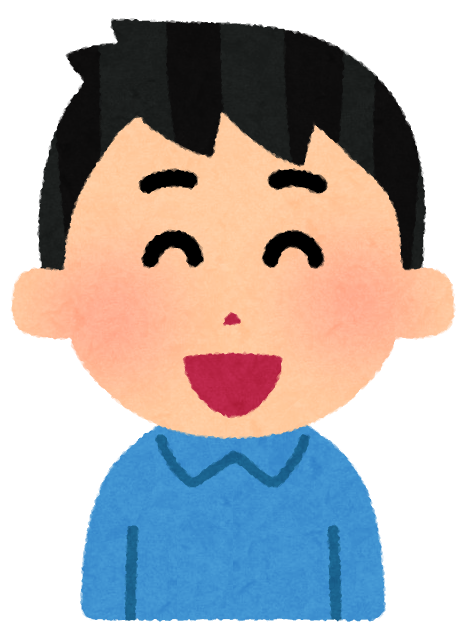
この記事を最後まで読んでいただければ、女王の教室が視聴者に何を訴えたかったのかが分かります。
この記事を書く僕は、以下のような人間です。
・小学校で教員をしている
・ドラマ・映画・アニメのメッセージから学ぶことが好き
何となく見ているものでも、見方によって、実は学べることはたくさんあります。
目次
女王の教室を見て感じた3つのこと
女王の教室を見て感じたことは以下の通りです。
①このドラマは教師対子どもの敵対構造ではない
②社会問題を訴えている
③神田和美がすごい
順番に解説していきます。
このドラマは教師対子どもの敵対構造ではない
はじめにも書きましたが、このドラマは一見子どもが団結して教師を倒すという構造に見えますが、久しぶりに見るとそうではありませんでした。
子どもどうしの敵対構造でした。
まず、このドラマは子どもどうしの浅い人間関係が顕著に現れていました。
初めは異常なくらい、めちゃくちゃ浅かったです。
・勉強のできる子は、勉強の苦手な人やクラスのことなんてどうでも良い
・クラスの人がピンチな時に誰も手を差し伸べない
・人の気持ちを考えず、自分が良ければ全て良し
・盗みをした犯人をすぐに悪者扱いしていじめる
見ているこっちがイライラするほどの浅い人間関係と子どもたちの敵対構造がありました。
元々潜在的にあったものが、真矢の指導や問題が起きるたびに顕在化していくというように捉えました。
社会の問題を訴えている
担任の真矢は、社会の現状についてズバズバ厳しいことを言うのですが、その内容はどれも今の社会の問題を表しているものばかりでした。
例えば、
・格差の問題
→遊園地で、ジェットコースターに並んで乗る必要もなく、順番を抜かして乗れる人が世の中にいる
→お金を払えばすぐに欲しいものを手に入れることができる。
・自分が良ければ全てよし
→自分が幸せになればそれで良い。周りが失敗してもどうでも良い
などなど
そんな社会システムを担任の真矢は包み隠さず子どもたちに伝え、クラスの子どもたちはそれを疑問視し、変えていこうと感じたのです。
真矢のクラスでは、まずはそのような社会システムをクラスの中で具現化しました。
子どもたちをテストで順位づけしトップの子には給食大盛り、ロッカーも使えるようにし、最下位の子には雑用係をさせるなど社会の現実と同じような仕組みをクラスの中で作りました。
テストで順位が上の人ははじめ、このシステムに納得している様子でした。勉強に集中できるし、雑用は全部順位が低い人がやってくれる、給食もたくさん食べれるから今のままが一番良いと感じていました。そんな彼らも、真矢に「何で勉強するの?」と聞かれたところ、「良い大学に入るため」としか答えることができず、それに対して真矢は「良いって何をもって良いって言えるの?」と聞かれると、ついに答えることができなくなりました。親に勉強しなさいと言われているから勉強しているだけに過ぎなかったのです。
勉強の目的に疑問をもったり、雑用係の人たちから「何で同じクラスなのに協力しないんだ?おかしいと思わないのか?」と言われ、順位が上の人たちも少しずつ自分の考えを変えていきました。
クラスの一人ひとりが、自分の生き方やクラスの様子について疑問をもち、より良い生き方を見出していっていきました。
クラス全体の問題解決能力も上がり、自分たちで良いものは良い、納得のいかないものは担任に訴えるというようなクラスのシステム、つまり社会のシステムを自分たちで変えるという子どもたちに育っていきました。
「今のクラスや社会は絶対おかしい」「自分たちで絶対変えてみせる」と思える子になってほしい、
これこそが担任の真矢の願いであり、全てが真矢の作戦でした。
神田和美がすごい
クラスをより良くしていったのは、担任の真矢の作戦もありましたが、何と言ってもこのドラマの主役でもある神田和美の存在が大きくありました。
担任の真矢は「自分の厳しさに耐えられる子は誰?」と、神田和美を軸にしてクラスを良くしていようとあらかじめ作戦を立てていました。
はじめから「みんな仲良くしたい」ということを何となく良いと感じており、かつ担任の真矢の鬼のように厳しい指導に耐えうる忍耐力をもっていたからこそ、色々ありましたが、このクラスはどんどん良くなっていきました。最終的に和美も、「仲良くしたいのはなぜだったのか」「仲良くするってどういうことをいうのか」の答えを自身の中で見出していきました。
いや〜!!すごすぎます!!
女王の教室を見て教員として学んだこと

教員として学んだことは次の通りです。
①子どもの行動の裏にある背景まで理解する
②子どもは子どもどうしの間で育つ【教員の役目は壁づくり】
③気に入られようとする教員でいすぎてはいけない
子どもの行動の裏にある背景まで理解する
クラスの中で勉強苦手で、担任の阿久津真矢に反抗的な態度をとる子がいました。
それが、まなべゆうすけでした。
反抗的なゆうすけの態度に対して、真矢はズバッと言いました。
「そうやって寂しいから注目されたいだけでしょ」と。
その後、厳しい学校に来なくなったゆうすけに真矢は会いに行きました、「学校に来いなんて言っても行きませんよ」というゆうすけの言葉に対し、真矢は「そんなわけないじゃない。」とまさかの卒業証書を渡すなど考えられないことをします。
和美に助けられながらもゆうすけは、
「逃げるのは簡単。真正面から戦う」
というように、気持ちを切り替え、学校に行くようになりました。
そして、クラスのムードメーカになり、さらには周りの子にも良い影響を与えていきました。
ゆうすけの成長は凄まじかったです。
そんかゆうすけですが、実はゆうすけには父母がおらず、おじいちゃん(おばあちゃん?)に育てられていたのです。
そういうゆうすけの寂しさを担任の真矢は分かっていたんだと思います。
また、
「だからと言って逃げていてはいけない。環境に左右されず自分の力で生きてほしい」
というゆうすけ対する真矢の願いがあったんだと思います。
その子の事実だけでなく背景に迫ること、気持ちを理解することができてこそ、その子のことを思った指導ができます。
卒業式には、ゆうすけのお母さんを探して来てもらうなど、心の底からゆうすけのことを考えていました。
※学校に来なくなったゆうすけに対し、卒業証書を渡すなど、やり方はどうかと思いますが笑
子どもは子どもどうしの間で育つ【教員の役目は壁づくり】
教師と子どもの一対一でのやり取りで育つことには限界があると感じました。
女王の教室でも、基本的には子どもたちどうしのやり取りの中でお互いに刺激し合い変わっていく様子がありました。
真矢が言っていた「子どもは子どもどうしの中で育つ」、本当にその通りだと思いました。
では、担任にできることは何でしょうか?
それは「壁をつくる」ことだと感じました。
この子なら、このクラスならこのあたりまでいけそうと目標を設定するということです。
実際に、真矢はその時に応じて目標のレベルを上げていきました。
子ども間の競争
↓
班での競争&連帯責任
↓
クラス全体で問題解決
↓
親に自分の生き方を訴える
連帯責任についてはどうかと思いますが、その時々で子どもの様子を見極めて、スモールステップで最終目標である、「自分はどのように生きていきたいか」というそれぞれの自立へと向かわせていきました、
クラス全体の成長だけでなく、個々の成長についても真矢は見極めていました。真矢の見極め力はずば抜けていました。
気に入られようとする教員でいすぎてはいけない
真矢の隣のクラスには、子どもたちと友達のような感覚で接する先生がいました。
その名も『天童先生』
カラオケに行ったり、一人の子と特別仲良くするなど、まさに友達!!
これに対して、真矢は「他の子はどう思っているのか考えた方が良い。」「あなたは、子どもたちに良い先生と思われたいだけ」と厳しく注意するのです。初めはその言葉に疑問視していた天童先生でしたが、真矢のクラスがどんどん良くなっていく様子を見て、真矢を尊敬するようになり、自身の教師としてのあり方を見つめ直していきました。
結果的に天童先生は次の年、黒い服を着て真矢のように厳しい教員になりました笑
子どもを甘やかすのではなく、厳しくも本当にその子を思って教育をした方が良いと思ったんだと思います。
このことから、「この先生は良い先生だ」と思ってもらうことが目的になってしまっていてはいけないと感じました。良い先生だなと子どもたちが感じることは、あくまでも結果。その時でもあれば何年か先かもしれません。良い先生であるかどうかを気にしていたら子どものためを思った本当に良い教育はできないと感じました。
教師のあり方を見つめ直す時も、「子どもに良い先生だと思ってもらえているか?」で振り返るのではなく、「あの時の関わり方や支援の仕方って本当に子どものためになっていたのか?」で振り返ることが大切だと思いました。
子どもに気に入られたい・好きでいてほしいと感じすぎてしまい、苦しいと感じていらっしゃる先生がいましたら、ぜひこちらの記事もご覧になっていただければと思います。
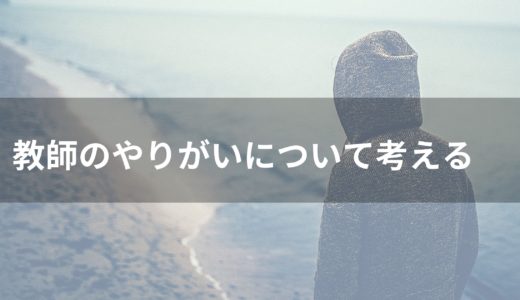 【先生やってて良かった】教師のやりがいはズバリこれ!!【卒業生が会いに来てくれた】
【先生やってて良かった】教師のやりがいはズバリこれ!!【卒業生が会いに来てくれた】
女王の教室を見て批判的に見る

ここまで、女王の教室すごい!!真矢すごい!!ということを書いてきましたが、少し批判的にも見てみたいと思います。
人に迷惑をかけてはいけないのか?
真矢は、「人に迷惑をかけるな」と何度も言いますが、本当に迷惑はかけてはいけないのでしょうか?
というよりも、迷惑をかけずに生きていける人っているのでしょうか?
真矢は、“あなたはありのままでいいんだよ”という見方がないように感じました。
努力こそ正義、自分のことは自分でやるが正義というスパルタ教育が強すぎているように感じました。もちろん子どもたちが社会に出て行った時を考えての指導ということは分かりますが、、、
それが、いきすぎると息苦しいかもしれません。
恐怖で従わせる
真矢が子どもの人権を無視していることは確かにその通りでした。
授業中トイレに行かせない、自分の悪口を言ってるかスパイをさせる、給食を食べさせない、机の上に罰として座らせる
などなど、、、
そういうことはあってはなりません。
ま、ドラマですが笑
まとめ【教育は奇跡が起きる】
真矢の毎日テストや恐怖で子どもを従わせるというやり方には賛成出来ませんが、教師としてのあり方としてかなり参考になる部分がありました。
最後に、
真矢はいろんな先生から「なぜ教師を続けるのですか?」という質問されるのですが、その質問に対して「教育は奇跡が起きるからです」と一貫して答えていました。
教育は奇跡が起きる
100%共感しましたし、めちゃくちゃ痺れました。
思いをもって仕事をすれば、そういう場面にたくさん出会えると感じました。
また、その中で子どもも教師も成長していくことがたくさんある、教師って仕事はやっぱり素敵だなと思ったドラマでした。
ドラマは学ぶこと多しです!!
最後までお読みいただきありがとうございました。
では!