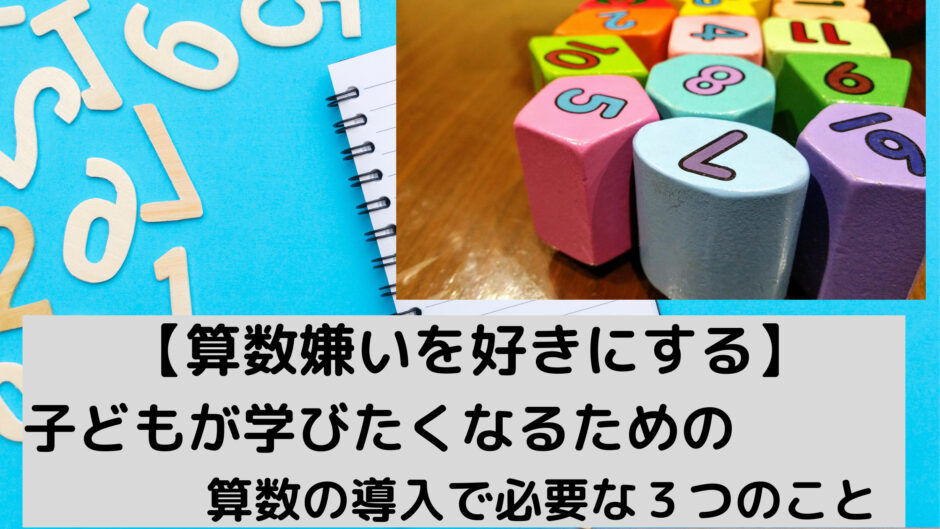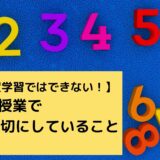・子どもが学びたくなる授業の導入の工夫が知りたい
僕は授業の中でも特に“導入の部分”をとても丁寧に行っています。
それは、子どもがこれから学ぶことに対して「学びたい!!」と思って学んでほしいと思っているからであり、そのために導入でどのように子どもの興味を惹きつけるかが何よりも重要であると考えているからです。
では、どのようなことを導入で意識すれば、子どもは「学びたい!!」と感じるでしょうか?
今回は、小学校3年生の算数の授業の中で、『小数』と初めて出会う場面を例にして解説していきます。
・算数の導入で必要な3つのこと
・『小数』の導入の実践例
・予定していた導入で興味をもたなかった子への対応
この記事を書く僕は、以下のような人間です
「小学校教員をしている」
「クラスでの練り上げ問題解決型の授業がものすごく好きで価値があると感じている」
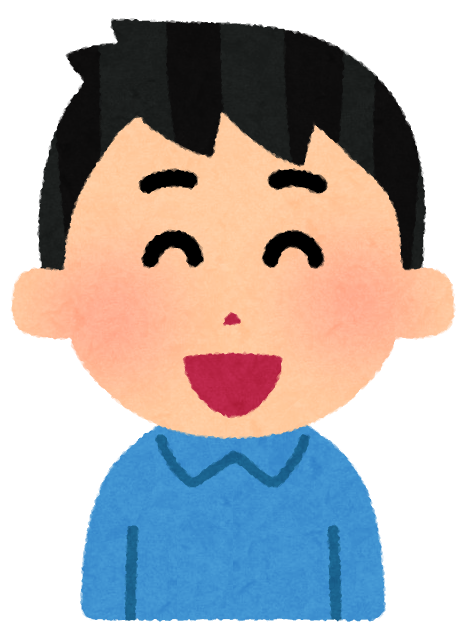
目次
子どもが学びたくなるための算数の導入で必要な3つのこと

算数の授業で必要なことは以下の3つです。
①具体物を用いた活動
②既習事項とのズレや違和感から生じる「考えたい・学びたい」
③ちょうど良い難易度
順番に解説していきます。
具体物を用いた活動
具体物を使うことは算数の授業では子どもの興味を惹きつけるために、とても効果があります。
特に、視覚からの情報が入りやすい子にとっては、イメージもしやすくなるためかなり有効に働きます。
なぜ、ここで具体物を用いるかというと、算数の授業には“目的意識”がとても大切だからです。
具体物を見たり、実際に操作したりする中で、“これってどうなんだろう???”と学びへの必要感が生まれれば、導入は大成功です。
また、生活に根ざした具体物を用意すれば、日常でも算数が密接に関わっていることを感じ、算数を学ぶ意味も感じやすくなります。
既習事項とのズレや違和感から生じる「考えたい・学びたい」
算数の単元は学年に応じて系統的にできています。なので、既習事項と新しい事柄を比べ、そのズレから“問い”を立ち上げることが可能です。
例えば、5年生での面積の学習
4年生までに面積の概念(1cm2がいくつあるか)ということと、長方形や正方形の面積の求め方を学んでいます。
そんな子どもたちが、5年生になると、今度は三角形の面積を求める勉強をしていきます。
「長方形や正方形の面積は“たて×よこ”で求められてたけど、三角形の面積ってどうやって求めるの??」
と問いが生まれるというようなイメージです。
このように、既習と新しいこと比較を丁寧に行うことで、新しい学びへの動機付けを生むことができます。
また、今知っていることと新しいことを明確に区別することが、子どもが今の自分の現在地を知るためにも大切になってくると考えます。
実際に、三角形の面積は、形を四角形に変形すれば面積を求められることを知り、その後は平行四辺形が登場し、その面積は三角形や四角形などこれまで学んだ形に変形すれば面積を求められることを学んでいきます。
算数は、例え新しいことでも、これまで学んだことをうまく組み合わせて使えば解けてしまうというなんとも面白い教科です。
ズレを楽しめるようになったら、もう最高ですね!!
ちょうど良い難易度
子どもたちにとって、学ぶ意欲が湧くためには、ちょうど良い難易度が必要だと考えます。
これはあくまで経験値ですが、簡単すぎると子どもは飽きてしまい、難しすぎると逆に諦めてしまいます。
※もちろん全員が全員そうではありませんが
でも、これは一理あると思います。
例えば、僕はギターを少々練習中なのですが、急に「X JAPANの紅を弾けるようになろう」と言われても、それは難易度が高すぎて無理です笑
逆に、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドかの練習をしよう」と言われても、それはそれでつまらないし簡単なので飽きてしまいます笑
つまり、僕にとって練習したくなるのは、ちょっと頑張れば弾けるようになりそうな曲ということになりますし、実際に練習していて“楽しい!!”と感じるのは、そういった曲です。
(例えば、RADのなんでもないやとか、菅田将暉さんのまちがいさがしとかが、めちゃくちゃちょうど良い難易度です。)
話は脱線しましたが、教師は子どもたちの現在地を見極めて、“ちょっと頑張ればたどり着けるところ”で授業を行うことが哀切です。
これは算数の授業に限らず、全ての教科の学習や生活指導にも同じことが言えます。
『小数』の導入の実践例
では、ここで一つの実践例として、小数の導入をどのように行ったか紹介したいと思います。
まず、僕自身が「なんで小数って存在するのかなあ?」と考えました。
いろいろ考えたり調べたりしていくうちに、「1よりも小さい数を分かりやく表したいから」「言いやすいから」という答えにたどり着きました。
そこで、「小数の分かりやすさと言いやすさ」に焦点を置いて導入を行いました。
教科書は一旦置いておき、ブロックゲームという形で行いました。
ルール
①2人で行うゲーム
②一人15個のブロックを初め持っている
③ジャンケンして勝てば、相手からブロックを1個もらう
④2分間行い、ゲーム終了後に自分の点数を数える
ゲーム終了後に、点数の数え方を伝えました。
「10個で1点です」と
すると、ちょうど10個や20個などキリの良い数になった子どもたちは、1点や2点と自分の点数を数えることができるのですが、中途半端な数になってしまった子どもたちは「自分の点数は何点なんだ???」と考え始めました。
そんな時、ある子が分数を使い始めました。
「1個は、1点を10等分したうちの1個だから、1/10になる。だから3個の場合は3/10点」
これを子どもたちと確認し、
「じゃあ、13個は何点になるの?」と聞くと、
「1と3/10点」と答えました。
すると今度はある子が、「何か言いづらい」と言いました。
「どこが言いづらいの?」と聞くと、
「分数のところが言いづらい」と言いました。
クラスの全員ではないですが、「整数と分数の言い方だとなんか言いづらい」と感じる子や、ちょっと違和感を感じる子が増えていきました。
そこで、【分数ではない、別の言い方を学ぼう!】ということで小数の学習に入ってきました。
1/10=0.1だから、3/10=0.3
つまり13個の場合は、1.3点
と言った形で、小数の表し方や、小数点の意味、1/10のくらいなどについて確認しながら、新しい数の言い方を学んでいきました。
これが小数の第1時でした。
その後は、毎時間ごとに学ぶ必要感を生み出すための工夫をしながら行っていきました。
このような形で、「これまで分数で表していたことが、小数という別の方法でも表せる良さ」をブロックゲームを通して感じ、小数への興味や小数を学んでいく動機づけになってほしいという願いももち、小数の導入を行いました。
予定していた導入で興味をもたなかった子への対応

導入は常に工夫して行っていますが、全員が全員そこで興味をもつことはまずないと思っています。
それなのにも関わらず、「みんなが興味をもったね」と思い込んだり、ましてそれを言葉にすることはあってはなりません。
興味をもっていない子からすれば、興味をもっていないのにも関わらず「みんな」なんて一括りにされたらたまったものではありません。
それは子どもを見ることができておらず、「みんなが興味をもてば良い」ということは教師側の都合に過ぎません。
「興味をもつことが正しいんだ」という価値観がもしあれば、尚さらおかしな話です。
なので、たくさん授業の工夫をしたけど「興味もたない子も中にはいるよね」くらいのスタンスがちょうど良いと思っています。
しかし、単に俯瞰して見て終わりではなく、子どもたちそれぞれがどんなことを感じているのか探っていく必要があります。
また、興味を引き出すためには、別の場合を引き合いに出したり、時間をもう少しとってより丁寧に対話を重ねていったりすることもその時に応じて必要になってくるかと思います。
これはもうその時の教師側の瞬発力の世界です。←このあたりのセンスは経験が物を言うと感じています。僕はまだまだです笑
おわりに
子どもが学びたくなる算数の導入で必要な3つのことについて書いてきました。
参考になる部分があれば幸いです。
僕もまだまだ学んでいる段階ですが、少しでも子どもが「今日の算数はこういうことで楽しかった」と感じられるように日々取り組んでいきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
では!
今回は主に導入について解説しましたが、全体的な算数の授業の流れについては、こちらの記事をご覧ください!
↓↓↓
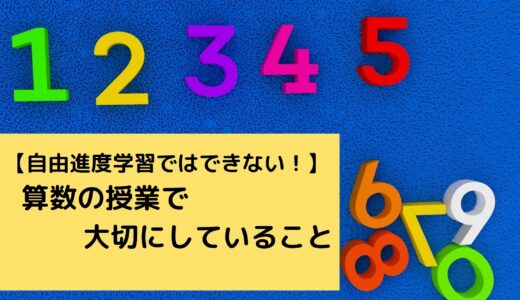 【自由進度学習ではできない!】算数の問題解決型授業で大切にしていること
【自由進度学習ではできない!】算数の問題解決型授業で大切にしていること