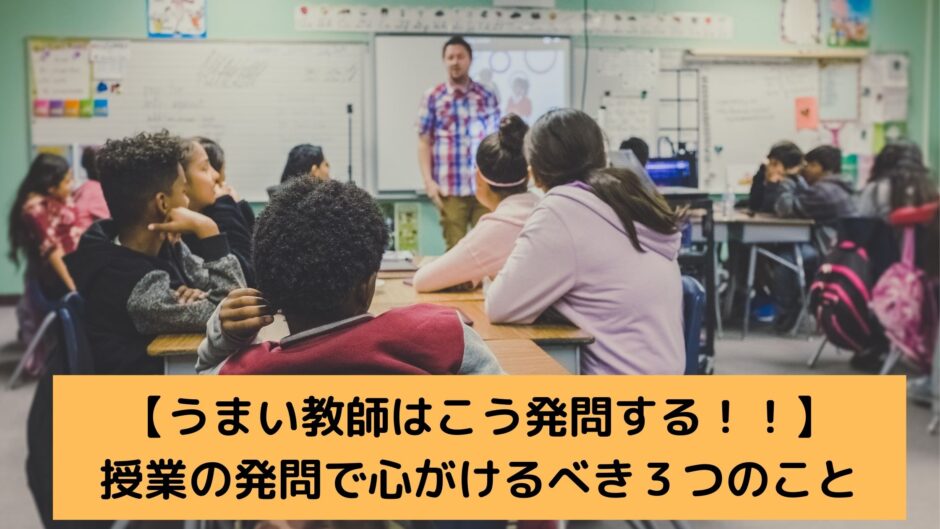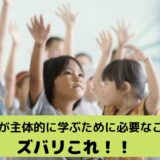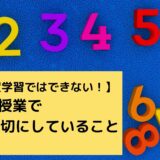・発問で気をつけることについて知りたい
授業において教師が子どもに問いかけることを「発問」と言います。
この発問は、ただ子どもが聞かれたことについて答えるためにしているのではありません。
発問には大きな目的があります。
それは、「子どもの考えを引き出す」ということです。発問は子どもの内在している考えを引き出すためにとても大切なものです。発問の精選は教師としてかなり重要なスキルの一つです。なぜなら、この発問によって、子どもが考えたくなるかどうか決まってくるからです。似たようなニュアンスの発問でもその言葉の選び方によって子どもの反応は大幅に変わってきます。例えば、「9+6ってどうして15になるの?」と「9+6をどう考えれば15になるの?」という一見似たような発問についてもそうです。最終的なゴールは“15になるわけを説明する”ということで同じなのですが、発問によって子どもの反応の仕方は変わってしまいます。子どもが答えたくなるもの・答えやすいものになったり、逆に答えたくなくなるもの・答えにくいものになってしまうものです不思議ですが、事実です。
発問が上手いかそうでないかによって、子どもの学びの質はもちろん授業の盛り上がりも大きく変わってきてしまいます。発問は授業作りの半分を占めるといっても過言ではありません。
では、発問をする際、どのようなことに気をつければ子どもの考えを引き出すことができるでしょうか。
・発問でこころがけるべきこと3つのこと
この記事を書く僕は、以下のような人間です
「小学校教員をしている」
「クラスでの練り上げ問題解決型の授業がものすごく好きで価値があると感じている」
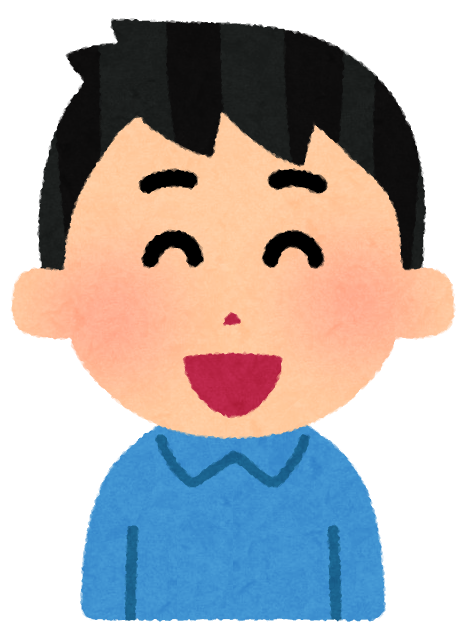
目次
発問で心がけるべき3つのこと
僕が発問で大切だと考えていることは以下の3つです。
①発問は短い言葉でスパッと言う
②教師の言葉は少なめにする
③教師対子どもの1対1のやりとりは少なくする
順番に解説していきます。
発問は短い言葉でスパッと言う
発問をした際によくありがりなのが、1回発問をして子どもの反応がなかったため、言葉を変えてもう一度発問し直してしまうというものです。
これは良くありません。
こうなってしまうと、子どもは一体何を聞かれているのか、何を答えれば良いのか、何を考えれば良いのか分からなくなってしまいます。
このようなことが起きたいために、発問は“短くスパッと”が大切です。
子どもの反応がなくても教師は少し待ってみることが大切です。(僕もなかなかせっかちなので待てないんです・・・)
教師の言葉は少なめに
問題解決型の授業であれば、教師はあまり話さないことを意識したいです。
なぜなら教師が話しすぎることにより、子どもの考える機会や時間が奪われてしまう可能性があるからです。
教師の話を聞いているだけでは子どもは自ら考え学ぶことができません。もっと子どもが考える場をたくさんつくっていく必要があります。
子どもの考えをより多く共有するからこそ、学び合い、自己の考えを深めることができます。
友達の考えから学べるようになったらもう最強ですので目指していきたいところです。
ちなみに発問を何回もする、発問し直すことも教師の話す言葉が多くなってしまう要因の一つなので、発問を含めた教師の言葉をなるべく減らし、もっと子どもの言葉で授業を進めていく必要があります。
教師対子どもの1対1のやり取りは少なくする
教師が発問をしたら、何人かの子がすぐに反応した後、教師は次の発問にいってしまってはいけません。
もし、すぐに次の発問にいってしまうと教師と子どもの1対1のやり取りになってしまいます。これは非常にもったいないことです。
反応した以外の子どもたちは、“誰かが答えてくれるから、自分は答えなくて良いんだな”となってしまいます。そして、授業への参加意欲がどんどん低下し、全員参加の授業とはほど遠くなってしまいます。
全ての子が考えることができるように、発問して反応した子が数人いた後に、教師が「続けてどう?」と聞いてみたり、書く時間を作ったりすることも大切です。
おわりに【何度も試しては修正することによって、発問選びのスキルアップをする】
発問は初めからうまくいくわけがありません。
特にクラスが変わって子どもが違えば、心に刺さる発問も変わってきます。
究極的には授業準備の時に発問を考えるのでなく、その時のクラスや授業の状況で発問が臨機応変にできるようになると良いのですが,これがなかなかに難しいです。
将来的にそのように真のプロフェッショナルになれるよう、今後も勉強していく次第です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
では!!