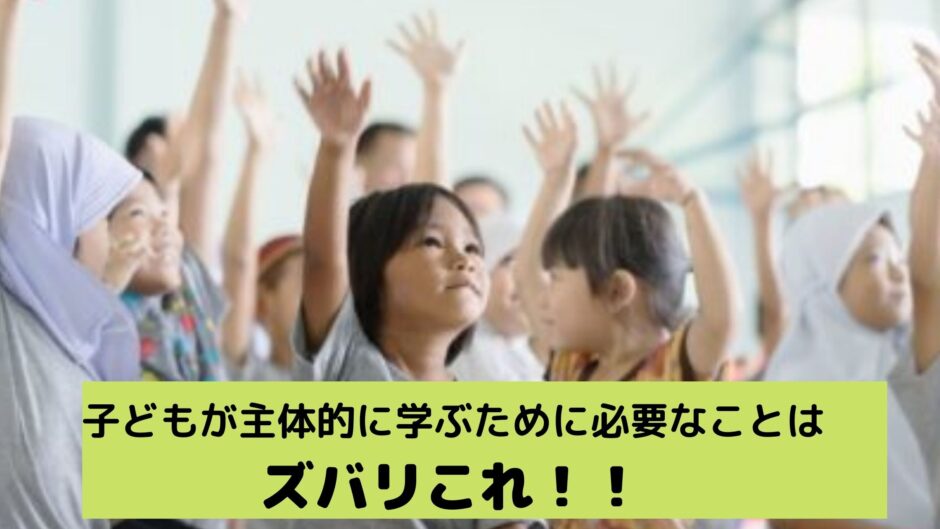・どのように評価して良いのか分からない
評価の3観点「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に取り組む態度」がありますが、その中でどのように評価して良いかと多くの方が迷うものはどれだと思いますか?
おそらく、一番最後の「主体的に取り組む態度」が最も多いのではないでしょうか?
改訂前の「関心・意欲・態度」とイマイチ違うニュアンスですし、人間の「主体性」を主観ではなく客観的な数値で評価することができるのか、また評価するとしたらどのように評価すれば良いのか疑問が多くあります。
また、「学びを調整している」ということや「学びを自覚している」ことが大切ということも言われていますが、子どもが自ら「学んでみたい」と感じるために必要なことって、それは子どもの力なのでしょうか?
主体的に取り組むために必要なこととして、子どもがもつべき力というよりももっと根っこにある、大切なことがあると感じています。
・子どもが主体的になるために必要なこと
・子どもの主体的な姿について問い直す
・正しい評価のあり方
この記事を書く僕は、以下のような人間です
「小学校教員をしている」
「子どもの主体性とは何か考えている」
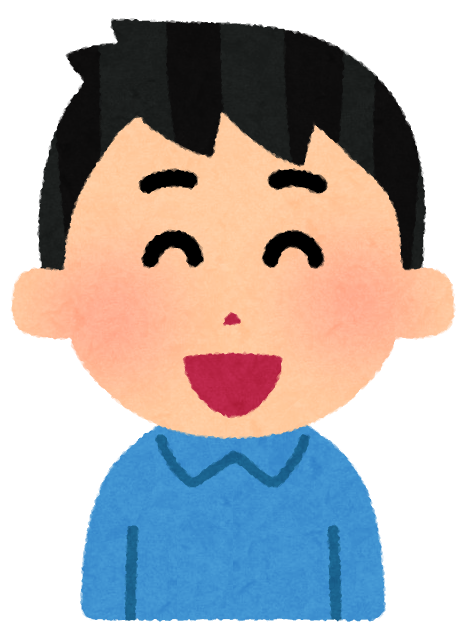
目次
子どもが主体的に学ために必要なこと【結局、授業が本人にとって面白いかどうかで決まる】
僕はこれ以上でもこれ以下でもないと感じています。
ここでの「面白い」とは、楽しいという意味も含まれますが、他にもこれは自分にとって必要がある・実りがあるという意味も含みます。
つまり、目の前の出来事が面白ければ、また 、自分にとって必要感のある問題、すなわち問題が“課題”となれば自ずと主体的になることができます。
〝この問題は解かずにはいられない〟状態になると、子どもたちは多いに主体性を発揮します。
また、良い大学に入りたい,頭が良くなりたいなど,明確な目標をもっている人は主体的になることができます。
ちなみにですが、この逆を考えてみると、自分にとって面白くもないし、必要感もない、将来役に立たないと感じている場合、主体的になることができるでしょうか。
なれるはずがありません。
テレビを見ることと置き換えて考えた時、興味のない番組を我慢してずっと見続けなければいけないことは、ただの苦痛でしかありません。
面白くない授業、必要感を感じていない授業を受けているということはこのような状態です。
このような状態に子どもがならないために、日頃から「子どもはどんなところで学びたくなるか」を探っていく必要があります。そして、子どもが目を輝かせながら学びに取り組む姿を目指して今後も授業づくりを行なっていきたいものです。
子どもの主体的な姿について問い直す
これまで言われてきた、子どもの主体的な姿について、僕はいくつか違和感を感じることがあります。
それは次の3つです。
①挙手して発言すれば主体的と見られること
②教師の言うことを聞いて素直に取り組むことが主体的と見られること
③人間関係の悪化により主体的になりたくてもなれな子もいるということ
順番に解説していきます。
挙手をすれば良い?
挙手をしている子のみが主体的と見られていることは多くあります。
もちろん挙手も主体的になれている一つの指標ではありますが、全部が全部挙手しているかどうかで決めるということはなくしていきたいです。
さらに言うと、挙手は“主体的に取り組めているか”を評価するにはあまりにも弱いと思います。
挙手をして発言はしなくても頭の中で一生懸命考えている、これも十分主体的であると言えます。
先生の言うことを素直に聞いて言う通りにする子どもが主体的なのか?
先生の言うことをきちんと守って、先生の理想通りに行動している子、そういう子は果たして主体的なのでしょうか?
これが、主体的かどうか聞かれると疑問です。
“先生の言われた通りに行動することは自分にとっての本当の願いなのか?”
僕は、これには2種類の子がいると思っています。
A:「先生の言ったことが自分も良いと思うから行う」という子
B:「“先生に認められたい”という承認欲求から言うことを聞く」という子
Aについては、自分の頭で考えて“良い”と感じたうえで行動しているので主体的であると言えます。
Bについては、承認欲求で止まっていて、自己実現としての行動ではないため、主体的であるとは言えません。
このように、同じ行動に見えても内面は全く異なっているため、注意深く見ていく必要があります。
そして、さらに問題提起したいのは新たなCのパターンの子についでです。
C:先生の言うことを聞かない子
子ども達は、一人ひとりやりたいことがあるし、その逆に“やりたくない”もある。そう考えると,先生の言うことを聞かないということも主体的であると言えると思います。先生のあらかじめ設定した枠の中においての主体的だけが主体的でないはずです。
しかし、ここでも大切なことは、“なぜ言うことを聞かないのか”の理由も踏まえたうえで最終的に主体的であるかないか考えるということです。
もしかして聞こえていない?認知能力が低い?集団に馴染むことができていない?自分との人間関係が良くない?、もしそうであれば、主体性を発揮することができない状態と見ることができます。
だいぶ話がそれてしまいましたが、一人ひとりのケースを考えることがとても大切です。
人間関係の悪化により主体的になれない場合もある
学習への興味はあるのに、人間関係が良くないため主体的になれない場合もあります。
例えば自分は意見を言いたいのに、意見を言ったら周りから
「優等生だなお前」
と言われる。
このような場合、到底主体的になることなどできません。周りからどのように見られるかということを優先に行動するようになってしまいます。小学校高学年や中学校などの多感な時期であれば尚更です。
ちなみにこれは僕の中学校時代の経験談でもあります。
大人になれば,「あなたに何と言われようが関係ない」となりますが,子どもにとって見れば,“自分が周りからどう見られるか”を気にしたり,周りと良好な人間関係を築いたりする方がむしろ先決なんです。
ですので、「この子は学習に興味がない」という決めつず、子どもどうしの人間関係はどうか見ていくということも必要です。
【提案】主体的に学びに取り組む態度の評価のあり方
ここまで書いてきたように、子どもが主体性を発揮するためには、その子にとっての学びの必然性やその子の自律の度合い、周りの環境等、様々な要因が関係してきます。
そのような中、子どもの主体的に学びに取り組む態度をどのように扱っていけば良いか提案したいと思います。
それは、
教師の授業改善・レベルアップのために使う
ということです。
授業の良し悪しで子どもが主体的になれるかどうか決まる面もあるのに、先生→子どもへの一方的な評価は果たして良いのでしょうか?自分の授業改善を常に考え続けなければいけないし,自分の授業に半分責任があるという視点ももって評価しなければいけません。
以前、僕の大尊敬する先生がこのように言っていました。
「俺たち教員が子どもを評価するなんておこがましい。俺たちの仕事は子どもの学びの土を耕し、芽が出てきたら水やりをすることだ」
この言葉に僕は、激しく心を打たれました。
この言葉を聞いて、自分自身、子どもを評価できるほど子どもを見れていないし授業もうまくできていない。僕が子どものためにできることは、子どものために自分が変わることが最も重要なことだと思うようになりました。
変わっていくためには、先生→子どもの一方的な評価ではなく、子どもからも授業に対しても評価をしてもらい、先生自身も改善していく営みが必要不可欠です。絶対的に自分のやり方が正しいわけはないですし、目の前にいる子ども達のために先生は存在するので、目の前の子どもに直接聞けば,それはもうお互いのためになりまくりです。
手短なところでいくと,「今日の授業どうだった?」とこちらから聞けば良い。そうすることで子どもは答えてくれます。
「もっとグループで考えたかったなあ」「先生が答えを言うんじゃなくて,自分たちで考えたかったなあ」などなど、、、正直に答えてくれれば尚更嬉しいです。
おわりに【そもそも全てが主体的でなければいけないの?】
これまでの話と一転しますが、僕は最近、“何もかも主体的になるって不可能なんじゃないか?”と思っています。
“全てに全力です!!”なんてことあり得ません。
周りの人に環境を作ってもらい、そこで受け身で勉強する。
これでも最終的には自分に還ってくる場合も十分あります。
受け身でも自分のためになることは山ほどあります。
受け身で学びたい人もいます。ただ,姿としてはそれが主体的であるかどうか見えづらいだけの話。
むしろ教師はそのような子に目を向け、頑張っている姿を認める・応援することが必要だと考えます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
では!!