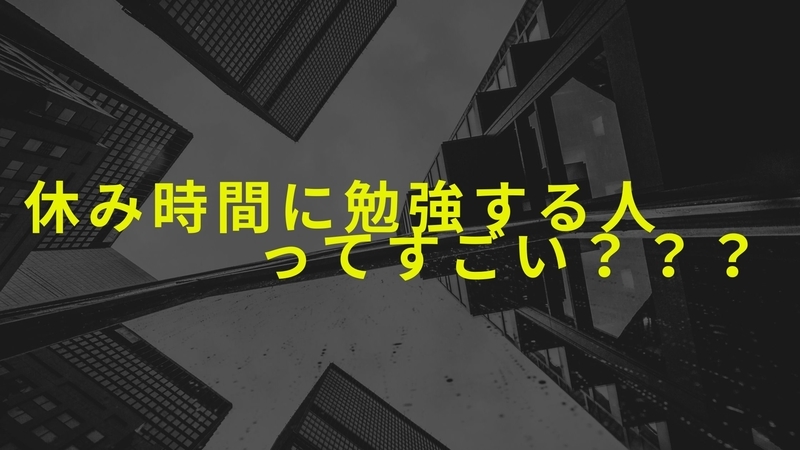目次
教師が二学期の学級びらきで気をつけること3選
僕が、二学期の学級びらきで気をつけた方が良いと考えることは次の3つです。
①「海に行った人?」とは聞かない
②全員に共通している話題を話す【オリンピックの話は全体の前ではしない】
③どんな夏休みを過ごし方一人ひとりを観察する
学校には鬼滅の刃を見ている子どもたちがとてもたくさんいます。
見ていない自分からすると,“なんでこんなに人気なの?”“何がそんなに面白いのかな?”と思うくらいです。
教室では鬼滅の刃の話が良くされています。ことあるごとに鬼滅の刃。休み時間には主題歌であるLiSAさんの“紅蓮華”を弾いたり,「先生,曲流して〜」という人も。
好きなことやものがあるって良いなあと思います。
しかし,この盛り上がった状況の中で気をつけたいことがあります。
それは,大ブームの中で,“見ていない人がいる”ということです。
今回はこのような流行に乗っていない子のことについて考えていきます。
1 流行に乗っていない子の気持ちに先生はとにかく寄り添う
ほとんどの友達が見ていてその話題で盛り上がっている中で,自分はその話題に乗れない。
それはとても“寂しい”ことではないかと思います。
その子は
“話題についていけなくてなんだか寂しい。だけど,自分はそれほど興味はないからその話題について知りたいとは思わない。どうしよう・・・”
こんな葛藤を抱えているように感じます。
考えるだけでもなんだかもどかしいです。
僕は,盛り上がっているように見えても,実はそこに乗れずに寂しさを感じている子を大切にしたいと思っています。
2 僕が流行に乗っていない子に寄り添おうと思ったエピソード
子どもたちが自分のやりたいプリントを選んで自主的に学ぶために,“自分の時間”というものを毎日1時間とっているのですが,ずっとやっていると疲れてしまうことを考慮して,鬼滅の刃のぬり絵を用意した時のことです。
この記事は続きがあります。閲覧料金をお支払いいただくことで最後までご覧いただけるようになります。または、公式line(https://lin.ee/cgSv844C)に登録していただくと、全ての授業コンテンツが月額2000円で閲覧できるようになります。